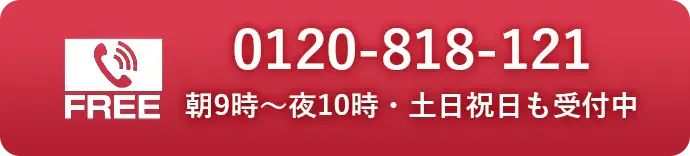よくあるご質問のピックアップ
- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?
-
事故を証拠に残しておくためにすべきことを、下記にご案内します。
1.必ず警察へ連絡してください
のちに交通事故証明書を取得する際の記録の根拠とするためです。
また、実況見分を行ってもらう上で、事故を警察に認識してもらうことは不可欠だからです。
2.加害者からさまざまな情報を取得
自動車のナンバー
これがわかると、後日陸運局で加害者車両の自動車登録事項証明書(いわゆる「車検証」です)を取得することができます。費用は、現在証明であれば300円です。
名刺
勤務先情報を入手することができます。
運転免許証
加害者の住所、氏名がわかります。
自動車登録事項証明書
とくに、ここでその自動車の所有者と運転者が違う場合、所有者の情報を記録しておいてください。運転者が経済的に困窮していて賠償が困難な事情があったとしても、所有者から賠償を受けられる場合があります。
加害者の自賠責保険、任意保険の会社名
通常、加害者個人では賠償できないので、保険会社がどこかという情報は非常に重要です。
加害者の事故直後の言い分の録音、メモ
事故から時間が経って、争いが出てきたときに、加害者が最初どう言っていたかということが重要な証拠になる場合があります。
3.現場の情報を証拠として残しておく
現場や破損した自動車の写真などを撮影するなどしておきましょう。
携帯電話のカメラ等でも構いません。車両が壊れてしまったことによる損害(物損)について争いになったとき、役に立つことがあります。事故状況をできるかぎり把握・記録しておきましょう。上記に加えて、保険会社との対応をスムーズにするために、自分の加入している任意保険会社へも連絡しておきましょう。ここまでやっておけば交通、交通事故直後の行動としては十分です。
- 交通事故によってケガをした被害者は、どのような請求ができるのでしょうか?
-
交通事故によりケガをした場合には、主に次のような様々な損害につき、賠償金を請求することができます。
治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などです。
休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。
入通院慰謝料
ケガをして、病院に入院したり、通院したりしている間に受ける「痛い」「辛い」という精神的苦痛を賠償するものです。
後遺障害による逸失利益
後遺障害が残ってしまった場合に、将来の労働能力に影響を及ぼすものとして、その分の賠償となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛を賠償するものです。
- 交通事故の過失割合はどうやって決まるのでしょうか?
-
裁判によらない示談交渉の場では、当事者双方の話合いによって決まります。
1.過失割合の基本的な考え方
裁判所、弁護士、保険会社のいずれも、原則として「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社。以下「本書」といいます)に従って決められています。具体的方法は、次のとおりです。
本書全訂5版では、あり得る交通事故の類型として338件の類型を挙げていますが(この類型内容、件数は改訂を経るごとに変更されていきます)、まず、事故がどの類型に近いかを調べます。たとえば、「信号機のある交差点での、自動車同士の出会い頭の事故」だったとしましょう。そうすると、本書全訂4版では、類型98から類型100までの3つの類型が用意されています。
これら3件を見比べると、「信号の色」が問題となっていることがわかります。次に、自分の車、相手の車がそれぞれ何色の信号のときだったかを思い出しましょう。
そこで、たとえばあなたの車が黄色、相手の車が赤だった、ということになりますと、類型52が合っているということになります。そこで、この類型の「基本割合」を見ると、20:80と記載されているので、特別な事情がないかぎり、あなたが20%、相手が80%という事故だということになります。
しかし、それで終わりではありません。その下に書かれている「修正要素」という項目を見ていきましょう。たとえば、あなたが赤信号の直前に交差点に進入したのだとすると、あなたの過失割合20%に10%が加えられることが書かれています。もしこのような事情があったとすると、あなたが30%、相手が70%ということになるのです。
ただ、実際には、これだけ類型が用意されているにもかかわらず、どの類型にもあてはまらない事例も少なからず存在し、そのような場合は、できるだけ似ている事案を参照しながら妥当な過失割合を考えていくことになります。ただ、類型と違えば違うほど過失割合の判断は難しく、訴訟になった場合の予測は困難となります。
2 過失割合を「決める」のは誰か?
以上のとおりが過失割合の考え方ですが、ご相談を受ける中で、「もう保険会社が過失割合を決めてしまったのだけれども、これに納得がいかない」などのお話をお聞きすることがあります。しかし、これは誤解でありまして、保険会社が一方的に過失割合を決めることはできません。あくまで、任意の話合の段階では、被害者の方と保険会社との「合意」があって初めて過失割合が決まるのです。ですから、保険会社がいう過失割合は、「保険会社の一方的な見解」に過ぎず、これに「合意」しなければ、過失割合が決まることはないのです。そして、このような「合意」ができないときは、最終的には訴訟になりますが、訴訟になった場合には、当事者の主張と提出する証拠を見て、裁判所が過失割合を決めることになり、これが最終判断となります。
3 過失割合でなかなか合意できない場合はどうしたらいいか?
たとえば、「交差点である」とか、「信号機がある」とか、「どちらも自動車だった」とか、「自分の走っていた道路は優先道路だった」などの事情は、交通事故証明書などで客観的に明らかなので、争いになることはありません。
しかし、「衝突のとき、相手が合図をしていなかった」とか、「衝突のとき、相手方の信号は黄色から赤色に変わる瞬間だった」などの事情は、上にご説明した「修正要素」として大変重要な事情ではありますが、とくに示談交渉の段階では、客観的な証拠がないことが多いので、深刻な争いになることがあります。このような場合、刑事記録を取得することが非常に重要です。ただ、刑事記録を取得すれば、それだけで被害者の言い分が正しいことが明らかになるとはかぎりませんので、そこからさらに資料の収集や交渉が必要となると思われます。
お互いの言い分が大きく食い違うような場合は、相手方との争いが相当長期間におよぶ可能性があるので、とくにお金のやりくりが難しくて当面の生活費にも困ってしまう状況にある被害者の方は、争いどころではない状況に陥ることがあります。そのような方は、自賠責保険の被害者請求をしたり、あるいは(あなたがかけている)人身傷害保険の保険金を請求したりすることを検討して、早めに賠償を受ける方法を考えたほうがよいでしょう。以上のとおり、過失割合をめぐる交渉では、色々な要素をバランスよく考えていかなければならず難しいものなので、知識、経験がある専門家に相談することをお勧めします。
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?
-
弁護士費用特約とは、被害者の方やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている「特約」であり、ご自身が交通事故に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものをいいます。
弁護士費用の負担限度額について
保険会社が負担してくれる弁護士費用の上限について、多くは下記のようにしています。
相談する場合:最大10万円
示談交渉を依頼する場合:最大300万円交通事故の相談や示談交渉では通常、上限内におさまることがほとんどです。
特約利用時の保険の等級について
交通事故で自動車保険を使用した場合には、等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性があります。
ですが、弁護士費用特約の場合は、使用しても保険の等級は下がらず、保険料が上がることもありません。特約利用対象者について
下記に該当する人が弁護士費用特約を利用することができます。
契約者
1の配偶者(内縁関係でも可)
2または2の同居の親族
1または2の別居の未婚の子
契約自動車に搭乗中の者
1~2に該当しない者で契約自動車の所有者
このように、弁護士費用特約は契約者ご自身以外も利用対象者となります。なお、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。
実際にご利用になる際には、契約している保険会社と弁護士にご相談ください。
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
-
通常は、示談成立後に追加で損害賠償を請求したり、示談内容を撤回することはできません。
しかしながら、示談のときに予測不可能だった痛みが発生した場合には例外的に請求が認められるケースがあります。示談時に予測することができなかった損害が発生した場合
示談書に後遺障害部分については別途協議するなどの文言があるケース
ただ、これは極めて例外的な事例ですので、そう簡単に示談の内容をひっくり返すことはできないと考えておいたほうが無難です。
ですから、示談をする際には、本当にその内容で問題がないかをしっかり調べて考え、すこしでも不安があるときは弁護士の意見を聞いたうえで損をしない示談をすることをおすすめします。
- 賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
-
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。
- 症状固定は、誰が判断するのですか?
-
症状固定かどうかを判断するのは主治医です。
症状固定とは、これ以上治療を行っても症状の回復が見込めない状態のことをいいます。一般的に、加害者の保険会社は「症状固定ですので、今後は治療費の支払いを打ち切ります」などと言ってくることが多いですが、保険会社はあなたの症状の状況を直接見ているわけではありません。
実際にあなたの症状を見ている主治医が症状固定日を判断するべきです。
また、保険会社の打診する打ち切り日が必ずしも症状固定となるわけではないため注意が必要です。
ただし、主治医であっても症状固定の判断は難しい問題であり、裁判所の判断する症状固定日と主治医の判断する症状固定日が必ずしも一致するわけではありません。
適切な症状固定日を判断してもらうためには、主治医に症状の内容をしっかりと伝えていただき、あなたの体の状況をよくわかっていただくことが重要です。
- 交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください.。
-
まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。
その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。保険会社は、裁判所基準に比べると大幅に低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士が、裁判所基準を基に保険会社と交渉することで慰謝料が大きく増額となる可能性がありますので、死亡事故の慰謝料については、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121