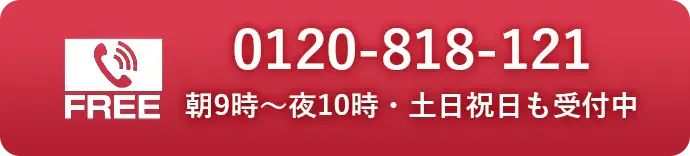- 警察の人から、加害者は、盗んだ車を運転中に事故を起こしたのだと聞かされました。 車の所有者に対して、損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
原則として請求できません。
車の所有者が、加害者の起こした事故について責任を負うのは、加害者に対し、車を使用することを許諾した場合が原則となりまず。例外的に、車の管理に落ち度があったために盗まれたという場合には、請求できることもありますが、極めてまれなケースであると考えられます。この場合には、加害者自身に対して請求をしていくことになります。
- 加害者の車検証を見たところ、加害者の名義になっておらず、車の販売会社名義になっていました。 販売会社に対して、損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
原則として請求できません。
加害者の車検証の所有者が車の販売会社となっているケースは、車の使用者が、車をローンで購入し、その購入代金をローンで返済中の場合であると考えられます。その場合でも、車の運転について、常に管理し使用しているのは、車検証上の使用者であると考えられるため、原則としてその車検証上の使用者または加害者自身が責任を負うことになり、車の販売会社は責任を負いません。
- 会社の従業員が事故を起こした場合、会社に対して損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
請求できる可能性があります。
事業のために他人を使用する者が事業の執行につき被用者が損害を第三者に与えた場合に、使用者が責任を負担することとなっています。これを使用者責任といいます。ご質問のケースの場合、使用者責任が認められるかどうかは、「事業の執行につき」といえるかどうかですが、業務時間中に社用で運転がされていた場合が典型例です。しかし、「事業の執行につき」といえるか、判断が難しいケースもありますので、弁護士にぜひご相談ください。なお、ご質問のケースの場合、会社に対しては、使用者責任だけでなく、自動車損害賠償保障法に基づく責任が認められる場合もあります。
- 加害者は未成年者でした。 その親に損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
親が運行供用者に当たる場合(車が親の所有名義である場合等)は、運行供用者として親に損害賠償を請求できます。
また、加害車両の所有者が子供である場合も、親が自動車を購入したり、ガソリン代や保険料等、維持管理費用も親が支出したりしているときには、親の運行供用者責任が認められるのが通常です。また、「親が相当の監督をすれば事故の発生を防止できたケース」「監督をしなければ事故の発生する恐れが高かった場合などに親が監督を怠ったケース」についても、未成年者の行為による損害の発生につき、少年の親に独自の責任が認められる可能性があります。たとえば、加害者が無免許運転・酒酔運転や信号無視を繰り返していたのを知りながら放置していたケースで、親権者に対して損害賠償請求をすることができるとした裁判例があります。
- 加害者は飲酒運転で事故を起こしたのですが、同乗者が飲酒運転を勧めていたことがわかりました。 同乗者に損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
請求できる可能性があります。
加害者と同乗者とは、加害者の行為による損害の発生につき、双方ともに落ち度があるわけですから、共同で責任を負うべきことになります。この場合は、加害者自身に対しても、同乗者自身に対しても、発生した損害全額を請求していくことができます。
- 事故に遭ったのが駐車場内でした。 駐車場の管理者に、損害賠償を請求できないのでしょうか?
-
請求は一般的には容易ではありませんが、駐車場の設備管理に落ち度があり、交通事故が常時発生するようなずさんな駐車場の管理状態であった場合には、請求できる可能性があります。
一時停止規制や速度規制等の必要な措置を講じておらず、一般利用者が相当な注意を払って車の運転をしていても、事故が起きることが必然であるような管理体制であった場合には、駐車場の管理者としてなすべき義務を果たしていなかったとして、請求できる場合があります。
- 加害者が事故を起こしたのは、違法駐車していた車に原因がありました。 違法駐車していたドライバーに損害賠償は請求できますか?
-
違法駐車自体にも、事故の発生に対して落ち度があると考えられるため、加害者と違法駐車の運転手とともに共同不法行為者として損害賠償を請求できる可能性があります。
この場合、たとえば加害者が80%・違法駐車運転手が20%の割合で悪い(落ち度がある)という話になったとしても、加害者と違法駐車運転手の両方に対し、その過失割合にかかわらず、損害の全額を請求していくことが可能です。
- 加害者に「交通事故の損害は自分が100%補償する」という念書を書かせました。 念書に基づいて本人へ請求できますか?
-
仮に念書を書かせたとしても、加害者本人が任意保険に加入していれば、その任意保険会社が損害賠償の請求先の窓口となり、示談交渉の相手方となります。また、加害者の任意保険会社と示談して賠償金を受け取った後では、加害者本人への請求はできません。
- 加害者への損害賠償請求の期限はありますか?
-
損害賠償請求権については、権利を行使せずに一定の期間を経過すると、その権利が時効により消滅(消滅時効)してしまい、被害者はその損害を回復することができなくなります。
損害賠償を請求していく場合、主に消滅時効が問題となるのは【1】加害者に対する損害賠償請求権、【2】自賠責保険会社に対する損害賠償額の請求権が考えられますので、以下に説明します。1.加害者に対する損害賠償請求権
「損害及び加害者を知った時」から5年で、時効により消滅してしまいます(民法724条)。通常であれば、傷害部分については事故日から5年、後遺障害部分については症状固定時より5年間で、請求権が時効消滅してしまう可能性があります。
※改正民法施行前の令和2年3月31日までに発生した事故については、施行日である令和2年4月1日時点で消滅時効が完成していない交通事故以外は、損害賠償請求権の傷害部分および後遺障害部分の時効は3年となります。なお、加害者が判明しない場合であっても、交通事故のときから20年を経過してしまうと、やはり損害賠償請求権は消滅してしまう可能性があります。時効を更新し、権利を保全するためには、裁判上の請求などの手段を取る必要があります。2.自賠責保険会社に対する損害賠償額の請求権
自賠責保険では、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に対し、直接に被害者請求または仮渡金の請求をすることができますが、これらの請求権は原則として交通事故があった日から3年以内です。なお、平成22年4月1日以前に発生した事故については2年とされております。
- 加害者への損害賠償請求の期限が迫っています。 どうすればいいでしょうか?
-
大至急、「時効の更新」または「時効の完成猶予」の手続きをしてください。
時効の更新とは、時効期間が進行しつつある状態を断ち切って、それまでの時効期間の経過をゼロにすることです。
時効の完成猶予とは、時効期間が進行を一時的に停止することです。更新と違い、それまでの時効期間の経過をゼロにすることはできません。
時効の更新や完成猶予の方法には、以下のような方法があります。1.請求
訴訟提起、支払督促の申立、和解の申立、調停の申立など裁判所を経由した相手方への請求は、その行為のみで時効の完成を阻止することができます。
ただし、訴えの却下や取下げが発生すると、裁判手続き終了から6ヶ月間の猶予期間を置いて時効の進行が再開しますので、注意が必要です。
相手方に電話や手紙などで「払ってくれ」と要求したとしても、それは、ここにいう「請求」にはならず、次に説明する「催告」になりますので、それだけでは時効の完成猶予の効果が生じるに過ぎず、更新の効力は生じません。2.催告
1で説明したとおり、裁判所を通さずに加害者または保険会社に対して「払ってくれ」と要求することを「催告」といいます。
催告をすると、催告のときから6ヶ月間は時効が完成しませんが、この期間内に1で説明したような裁判上の請求(調停申立、訴訟提起など)をしないと、時効は完成してしまいます。
一度催告をした後、6ヶ月以内に再び催告しても時効の完成猶予の効力は生じませんし、時効完成までの期間がさらに6ヶ月延長されることもありませんので、注意が必要です。相手方に対し催告をしたこと証明するため、内容証明郵便(配達証明付き)で行うのが一般的です。
3.承認
加害者または保険会社に対して債務の承認を求めます。加害者または保険会社が、損害賠償責任や保険金支払債務の存在を承認すれば、時効が更新されます。
また、通常、任意保険会社は、示談解決していない場合でも治療費を医療機関に支払います(ケースによっては、休業損害も被害者に支払うことがあります)。
これは、損害賠償責任や保険金支払債務を認めているからこそ支払いを行っていますので、同様に時効の更新事由となります。
このときは、最後の支払をしたときから新たに時効期間が進行しますので、最後の支払がいつかによって時効完成の時期が決まります。
また、示談案として任意保険会社が一定の支払額(損害額計算書等)を提示していれば、これも債務の承認となりますので、その提示したときから新たに時効期間は進行します。4.協議する旨の合意
令和2年4月1日の改正民法施行により、新しく導入された完成猶予の事由です。
これは、当事者間で権利についての協議を行う旨の書面による合意があったときは、次のいずれかの早いときまでの期間、時効は完成しません(改正民法第151条)。その合意があった時から1年経過した時
その合意において当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過した時
当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時
この合意は通算5年間まで認められますが、2の催告による時効の完成猶予期間に合意を行っても時効の完成猶予の効力は生じないため注意が必要です。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121