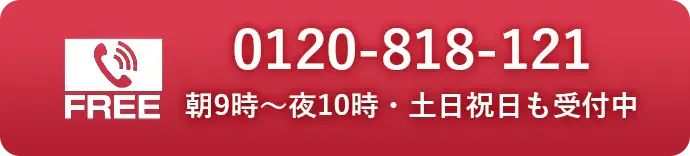- 交通事故に遭ったら、まずどうすればいいのでしょうか?
-
事故を証拠に残しておくためにすべきことを、下記にご案内します。
1.必ず警察へ連絡してください
のちに交通事故証明書を取得する際の記録の根拠とするためです。
また、実況見分を行ってもらう上で、事故を警察に認識してもらうことは不可欠だからです。
2.加害者からさまざまな情報を取得
自動車のナンバー
これがわかると、後日陸運局で加害者車両の自動車登録事項証明書(いわゆる「車検証」です)を取得することができます。費用は、現在証明であれば300円です。
名刺
勤務先情報を入手することができます。
運転免許証
加害者の住所、氏名がわかります。
自動車登録事項証明書
とくに、ここでその自動車の所有者と運転者が違う場合、所有者の情報を記録しておいてください。運転者が経済的に困窮していて賠償が困難な事情があったとしても、所有者から賠償を受けられる場合があります。
加害者の自賠責保険、任意保険の会社名
通常、加害者個人では賠償できないので、保険会社がどこかという情報は非常に重要です。
加害者の事故直後の言い分の録音、メモ
事故から時間が経って、争いが出てきたときに、加害者が最初どう言っていたかということが重要な証拠になる場合があります。
3.現場の情報を証拠として残しておく
現場や破損した自動車の写真などを撮影するなどしておきましょう。
携帯電話のカメラ等でも構いません。車両が壊れてしまったことによる損害(物損)について争いになったとき、役に立つことがあります。事故状況をできるかぎり把握・記録しておきましょう。上記に加えて、保険会社との対応をスムーズにするために、自分の加入している任意保険会社へも連絡しておきましょう。ここまでやっておけば交通、交通事故直後の行動としては十分です。
- 交通事故証明書は、どのように入手したらよいのでしょうか?
-
「自動車安全運転センター」というところに申込をして入手します。
入手方法は、【1】郵便振替による申込、【2】直接窓口による申込、【3】自動車安全運転センターのホームページ経由での申込の3つの方法があります。郵便振替による申込は、【1】郵便振替用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料(1通あたり800円(税込))を添えて申し込むという方法です。
直接窓口による申込は、【2】センター事務所(全国各地にあります)の窓口において、窓口申請用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて申し込むという方法です。交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所または郵送希望宛先へ郵送されます(他府県での事故の場合は、後日郵送となります)。詳しくは、同センターホームページをご参照ください。
- 弁護士に依頼をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
-
弁護士に交通事故被害の依頼をする主なメリットは以下のとおりです。
- 慰謝料などを増額できる可能性が高まる
- 保険会社への対応を一任できる
- 適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害として認定されると後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
適切な等級の認定により、賠償金額が増額する可能性がありますが、後遺障害等級認定の申請手続は複雑です。法律的・医学的な専門知識も必要となるため、交通事故に詳しい弁護士に対応してもらうことをおすすめします。
また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するものではなく、知識と経験の差が大きいです。
実は、保険会社の提示してくる示談金は保険会社独自の基準に従っており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)を大きく下回ります。
そのため、示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。
これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準に従って適切な賠償を受けられる可能性が高まるのです。
- 弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
-
基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけます。
ご不明点や不安・疑問など、何でも結構です。ぜひご連絡ください。
- 交通事故でケガをしたのに警察への届け出が物損事故扱いです。今後の手続で不利になりますか?
-
ケガをしているにもかかわらず、警察に人身事故ではなく物損事故として届け出た場合、加害者の保険会社からケガに関する補償の支払いを拒絶されてしまうことがあります。
たとえば、以下のような不利益を受ける場合があります。入通院慰謝料、休業補償が受けられないおそれがある
後遺症が残っても後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が受けられないおそれがある
実況見分が実施されないことにより、過失割合が不利になる可能性がある
警察や加害者から物損事故で処理したいと言われたことや、その場ではケガをしていないと思っていたことにより、安易に物損事故のまま処理をしてしまうと、被害者に不利益が生じます。ただし、すでに物損事故で届け出をしてしまっている場合でも、人身事故へ切り替えることは可能です。
下記の手順で手続ができます。- 病院で診断書を作成してもらう
- 診断書と切り替えの申請書類を警察に提出する
- 実況見分をおこなう
なお、事故から時間が経つと「ケガと事故の因果関係が判断できない」として、人身事故への切り替えができない場合があるため、申請は早めにおこないましょう。
また、ご自身が加入する保険会社と加害者側の保険会社へ、人身事故へ切り替えることを必ず報告してください。
- 警察から「交通事故から時間が経っているので、物損事故から人身事故への切り替えはできない」と言われてしまいました。どうしたらよいですか?
-
交通事故から長期間経過してしまった場合には、ケガと事故との因果関係が明らかではない等の理由から、物損事故から人身事故への切り替えができないことがあります。
このような場合には、もはや人身事故の交通事故証明書を入手することはできません。しかし、自賠責保険金については「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出すれば、請求できる余地があります。この理由書については、保険会社に問い合わせてみてください。
- 加害者は、どうして交通事故を物損事故扱いにしようとするのですか?
-
加害者が交通事故を物損事故扱いにしたがるのは、刑事処分や行政処分を受けることを避けたいからです。
人身事故の場合、加害者は刑事処分を受ける可能性が高いです。■刑事処分:罰金、禁固や懲役等の刑事罰が加害者に科せられて前科がつくことがある
■行政処分:違反に応じた点数が加害者に加算され、その点数が一定の点数に達した場合には、免許停止や免許取消しとなることがある
物損事故扱いの場合には、刑事処分、行政処分のいずれの処分も受けません。ですから、加害者にとっては物損事故扱いにしたほうが圧倒的に有利になるのです。
- 弁護士に依頼すると、必ず裁判になってしまうのでしょうか?
-
弁護士に依頼したからといって必ず裁判になるとは限らず、交渉で解決するケースが多いです。
弁護士が交通事故の被害に関する示談交渉をお引き受けした場合、基本的には加害者側の保険会社との話合いによる解決を目指して進めていきます。話合いから交渉を始めることで、早期解決にも繋がります。交通事故の被害にあわれた方は長くて苦しい治療期間を経ていますので、1日も早く適切な賠償金が支払われるよう、弁護士が示談の成立を目指します。
ただし、話合いによる交渉で、賠償額を安易に妥協することは決してありません。一般的に、保険会社は自社の支払基準(任意保険基準)に基づいて賠償金を算定してきます。これに対して弁護士は、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」を前提に示談交渉を行います。
弁護士基準と比べると任意保険基準は賠償金の算定額がかなり低めに設定されています。そのため、弁護士が交渉することにより、慰謝料や逸失利益などの賠償金の大幅な増額が期待できるのです。詳しくは、「交通事故の交渉を弁護士に依頼するメリット」のページをご覧ください。
そして、交渉により解決の見通しが立たないときに、そのほかの手続を行うことになります。そのほかの手続には、紛争処理センターの利用、調停の申立て、訴訟の提起などがあります。
弁護士に依頼すると、裁判など大ごとになってしまうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞ安心してご依頼ください。
- 物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?
-
物損事故から人身事故に切り替える手順は下記のとおりです。
①病院で「事故日」と「初診日」が記載された診断書を作成してもらいます
②診断書と切り替えの申請書類を警察に提出します
③警察による実況見分や書類の確認調査などをおこないます①病院で「事故日」と「初診日」が記載された診断書を作成してもらいます
事故のあと数日経って痛みが出てきた場合、まず病院で診察を受け、医師に診断書を作成してもらいましょう。
診断書は物損事故から人身事故に切り替えるために必要な書類ですので、ケガの程度にかかわらず必ず作成してもらってください。
診断書の作成にかかった費用は加害者側に請求できますので、領収書を保管しておきましょう。②診断書と切り替えの申請書類を警察に提出します
管轄の警察署に行って、診断書と申請に必要な書類を提出してください。
事前に連絡して予約するとスムーズに進めることができます。【申請に必要な書類】
- 運転免許証
- 車検証
- 自賠責保険証
- 印鑑
③警察による実況見分や書類の確認調査などをおこないます
被害者・加害者双方が立ち会いのもと、実況見分が行われます。
警察が事故発生当時の状況や事故車両の被害状況などを確認し、「実況見分調書」を作成します。すでに物損事故で届け出をしてしまっている場合でも、人身事故へ切り替えることは可能です。
ただし、事故から時間が経つと「ケガと事故の因果関係が判断できない」として、人身事故への切り替えができない場合があるため、できるだけ早く申請しましょう。
また、ご自身が加入する保険会社と加害者側の保険会社に、人身事故へ切り替えることを必ず報告してください。
- 交通事故被害者です。加害者の刑事処分の結果を知りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
-
事件を担当した警察署に問い合わせれば、捜査の状況などについて支障のない範囲で知らせてもらえます。
刑事処分の結果を知るための流れは下記のとおりです。- 事故を担当した警察署に問い合わせる
- 検察庁に問い合わせる
- 担当検察官に情報を確認する
1.事故を担当した警察署に問い合わせる
まず、交通事故証明書に記載されている事故を担当した警察署に電話をかけましょう。この際、以下の事項を伝えてください。
- 交通事故証明書に記載されている事故の内容(発生日時、場所など)
- ご自身がその事故の被害者であること
- 事件が検察庁に送られた(送致された)かどうか
事件がまだ警察署にとどまっている場合
この段階ではまだ刑事処分は決まっていません。警察官に「事件が検察庁に送られるタイミングで、検察庁の連絡先や事件番号(検番)を教えてほしい」と伝えておくとよいでしょう。また、警察に対して「被害者等通知制度を利用したい」と申し出ておけば、その後の情報が通知される可能性があります。
事件が検察庁に送られている場合
警察官から、どこの検察庁に送られたのか、および検察庁で事件を管理するための番号である「検番」を確認してください。
この情報は、検察庁に問い合わせる際に必要となります。2.検察庁に問い合わせる
事件が検察庁に送られたことを確認後、その検察庁に電話をかけます。
電話では、以下の事項を伝えてください。
- 交通事故の被害者として、加害者の刑事処分の結果を知りたい旨
- 加害者の氏名
- 警察で確認した「検番」(事件番号)
- 交通事故の発生日時や場所などの詳細情報
担当部署(通常は交通事件を扱う部署)に繋がり、必要な情報を伝えると、担当の検察官に取り次いでもらえることがあります。
3.担当検察官に情報を確認する
担当の検察官に繋がったら、以下の重要な情報を確認しましょう。
加害者が「起訴」されたか「不起訴」となったか
起訴は、 検察官が加害者を刑事裁判にかけると判断した場合です。
不起訴は、 証拠不十分などの理由で、刑事裁判にかけないと判断した場合です。
不起訴の理由(例:嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予など)も確認できる場合があります。裁判が確定しているかどうか(加害者が起訴された場合)
裁判が確定している場合、その刑事処分の最終結果(例:懲役〇年、禁錮〇年、罰金〇万円など)が判明します。この情報は、後日、実況見分調書や供述調書といった刑事記録を取り寄せる際に必要となる場合があります。
被害者等通知制度の活用
上記のような個別での問合せに加えて、被害者等通知制度を利用することも有効です。これは、検察庁に対し、加害者の刑事手続きの状況や結果について通知を希望する旨を伝えておく制度です。
一度希望を伝えておけば、その後の手続の節目ごとに検察庁から書面などで結果が通知されるため、ご自身で何度も問い合わせる手間が省けます。
検察官に問い合わせる際に、この制度の利用希望も伝えておくとよいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121